いよいよ金融機関も参入!北米で競争が激化する個人間送金サービス市場の現状
INDEX
クレジットカードやデビットカード、「PayPal」のような決済サービス、さらには電子マネーの普及によって現金を必要としない“キャッシュレス”な社会が確立されつつある。
スーパーマーケットで数ドルの支払いにもクレジットカードを使う北米では、現金を持ち歩かない人も少なくない。とはいえ、未だに”個人”へお金を払わなくてはいけない場合は不便に感じることがある。共同購入した同僚のプレゼント代や食事代などがそうだ。
そんな個人間のお金のやり取りを楽にしてくれるのが、P2P決済サービスだ。1対1を意味する“P2P”は、Peer to PeerまたはPerson to Personの略称だ。信頼できる相手とのお金のやり取りを、スマホアプリ(またはウェブサイト)だけで完結させられる。
競合がひしめくこの分野だが、基本的なサービス内容は共通している。銀行口座やデビットカードなどを連携させることで、P2P決済サービスが中間業者となって個人間の支払いを行ってくれるのだ。デジタルウォレットとして機能することで、お金を残高としてアカウントに保管しておけるサービスもある。
日本にも「Kyash」や「paymo」、「LINE Pay」など同様のサービスが登場しているが、日本では未だに現金払いが多いせいか、消費者は現金を使うことの不便を感じにくい現状がある。また、北米と違って事前の本人確認が必要という点も利用障壁を高める要因になっている。
調査会社のJavelin Strategy and Researchによると、北米におけるモバイルP2Pユーザーの数は2015年時点で6,900万人だったという。それが2020年までには1億2,600万人にまで増え、2021年には消費者の2人に1人がP2P決済サービスを活用することが予測されている。
北米のP2P決済サービス市場には、スタートアップやIT企業大手、銀行などがこぞって参入している。Appleは2017年6月に「Pay Cash」を発表。同時期に、開始時点で金融機関30社以上が参画するという「Zelle」もリリースされた。
盛り上がりを見せる個人間送金市場を制するのは、果たして誰なのか。ミレニアル世代を中心に急成長を見せるVenmoを筆頭に、IT企業大手や金融機関によるP2P決済サービスについて紹介する。
使い勝手と手数料ゼロがミレニアルを魅了する「Venmo」
2009年に登場したP2P決済サービスが「Venmo」だ。ユーザー数は公表されていないが、2016年最終四半期だけでトランザクションの累計額は前年同時期比126%に当たる56億ドルを記録した。
2013年に同サービスを買収したPayPalによると、Venmoによる送金の平均金額は1.5〜2.0ドル(2015年7月時点)。1ドル100円換算で150〜200円とかなり少額だ。この安さは、支払いの目的で食事代が最も多いことに起因しそうだ。
金銭的余裕のない学生が、安く上がるピザやチャイニーズフードなどを複数人で分けていることが想像される。とはいえ、ほかにもパーティの経費精算からルームシェアの家賃の支払いに至るまで、幅広い用途で使われているという。
VenmoにはメールアドレスやFacebookアカウントでユーザー登録できる。銀行口座またはデビットカードを連携させることで、Venmoのデジタルウォレットにお金を出し入れできる仕組みだ。
お金を支払う相手はFacebookアカウントや電話番号で見つけるほか、今月リリースされた「Venmo Codes」でQRコードにも対応した。
若い世代にVenmoが魅力的に映る理由はそのシンプルな使い勝手もあるが、一部を除いて手数料無料で使えることが大きいだろう。クレジットカードで送金する場合だけ、3%の手数料が発生する。

だが、Venmoがミレニアルに支持される最大の理由は、そのソーシャルな要素にある。
送金するには相手と友人関係になる必要があり、Venmo独自の簡易SNSも存在する。タイムラインには、友人間のお金の流れ(金額は非公開)が流れてくるため、「誰が、誰と遊んだのか」のアクティビティログになる。
また、送金の理由をメモする欄があり、気の利いた文言や絵文字などが飛び交っている。PayPalのCEOであるDan Schulman氏によると、「送金の90%以上で絵文字が使われている」という。トランザクションは非公開にもできるが、全体の90%が公開されている。P2P決済サービスでありながら、Venmoは人気SNSのようにリア充感をアピールする場になっているのだ。
2016年1月からは、小売業者がVenmoを支払いオプションとして提供できる「Venmo for Business」を開始した。 初期の導入サービスには、フードデリバリーの「Munchery」やチケット販売の「Gametime」などが参画。
まだマネタイズはできていないVenmoだが、小売業者から手数料を徴収することでそれが可能になる。一方、ユーザーにとっては個人間のみならず、日常的な買い物までVenmoを使って支払えることで利便性がさらに高まるだろう。
大手IT企業や金融機関の参入で激化する競争
Venmoのソーシャルな側面が若い世代を惹きつけているのだとすれば、FacebookやSnapchatといったSNSによるP2P決済サービス領域への参入は、ごく自然な流れだと言える。
Snapchatは2014年11月に「Snapcash」をリリースし、Facebookもまた2015年3月にFacebookメッセンジャー内で使える友人への送金機能をリリースした。どちらもデビットカードを連携させる仕組みだが、Snapcashが決済サービス「Square」を使っているのに対して、Facebookはシステムを独自に開発。双方とも、Venmoのようにお金を残高として残す仕組みはない。
2017年6月にP2P決済サービスへの参入を発表したのが、Appleだ。「Pay Cash」は同年秋のリリースを予定するiOS 11からサービス開始予定。ユーザーには、Apple Payの機能の一貫としてバーチャル口座が与えられ、銀行口座を連携させることでお金の入出金ができる。お金のやり取りは、友人知人とのコミュニケーションに使われるiMessageで行うこともあって、iPhoneでしか使えないという弱点がある。
Appleの競合であるGoogleもまた、2015年9月からAndroidとiOSの両プラットフォームで「Google Wallet」を提供している。クレジットカードを使った送金には手数料が発生するサービスが多いが、Googleは無料だ。
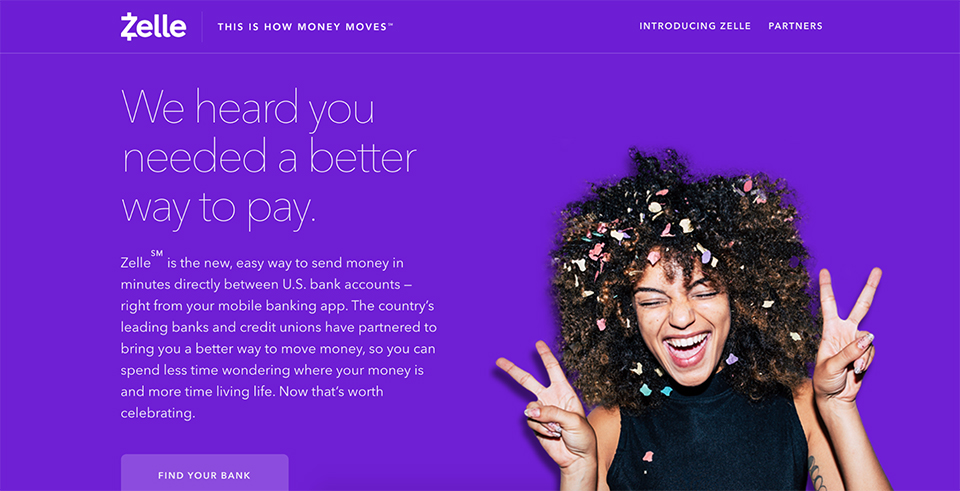
だいぶ出遅れたものの、今年6月に巻き返しを図って大きな一手を投じたのが金融機関だ。
これまで各社が独自に提供してきたP2P決済サービスを、ひとつに統合した「Zelle」で提供していく。開始時点で30機関が加盟し、各社のモバイルバンキングの利用者数の合計は8,600万人に及ぶ。参画する金融機関には、Capital One、Wells Fargo、JPMorganなどが含まれる。
年内には専用アプリのリリースを予定しているが、各社のアプリにZelleが搭載されるため、ユーザーはこれまでと同じアプリを使うだけでいい。相手のメールアドレスまたは電話番号があれば送金でき、数分以内に完了するという。手数料の決定権は各金融機関にあるものの、競合他社が無料とあって倣うところが多いようだ。
海外送金は?P2P決済サービスの展望
メジャーどころは押さえたが、P2P決済サービスは他にも「Square Cash」や「Dwolla」、「Xoom」などいくつも存在する。現状、各社のサービス内容には大きな差異がない。
だからこそ、ユーザーにとってはお金のやり取りが発生する友人知人が使っているサービスが最大の選択要因になる。SNSのように、ユーザーが増えれば増えるほどサービスの価値や利便性が向上するネットワーク効果が発揮されるわけだ。
前述のVenmoがミレニアル世代に支持されるのは、周囲のミレニアル世代が利用しているからに他ならない。2025年までに、北米では労働収入の46%をミレニアル世代が稼くと見込まれている(First Data調べ)。未来の消費を握るミレニアル世代を囲い込んでいることは、Venmoの最大の強みだろう。
一方で、金融機関が共同提供するZelleの加盟企業は今後も増え続け、それはそれでより上の年齢層に対してネットワーク効果を発揮するはずだ。
各社のサービスを大きく差別化する点があるとすれば、それは海外送金かもしれない。今回紹介したサービスは、どれも北米国内での送金が対象。唯一、Venmoの親会社でもあるPayPalに関しては「Xoom」でP2Pの海外送金に対応している。
Xoomは、2015年11月に買収されてPayPal傘下に入ったサービスだ。世界50ヶ国に対応しており、相手のPayPal電話番号またはメールアドレスがあれば送金できる。手数料はPayPal Walletへの送金が送金額の0.30%、相手の銀行口座への送金には9.99ドル以上がかかる。海外送金に関しては、Facebookもヨーロッパを手始めに対応することが噂されている。
大手IT企業や金融機関の参入でますます競争が激しくなってきたP2P決済サービス市場では、誰にも手を休める暇はない。金融機関が望みを託すZelleがリリースされた同月には、Venmoが通常1〜2日かかる送金を25セントで数分以内に完結できるオプションサービスを発表している。
これまで異なる銀行間でお金のやり取りがあったように、ユーザーがP2P決済サービスを同時に複数併用することは十分に考えられる。いずれかは集約されて淘汰されていくことになるだろうが、まだしばらくは熾烈な戦いから目が離せなさそうだ。
