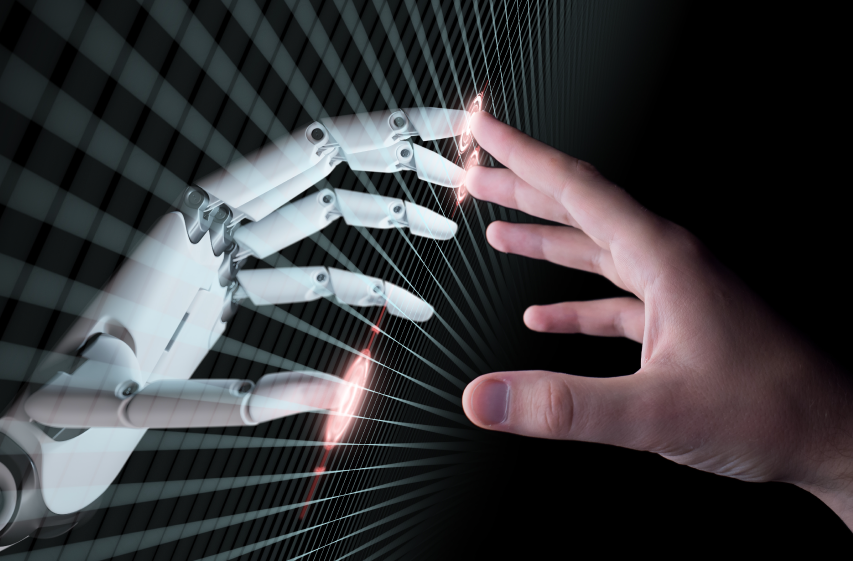漫画の世界がリアルになる「超人スポーツ」
「超人スポーツ」という言葉をご存知だろうか。
言葉は聞いたことがあっても、その具体的な内容はよくわからない、という人も多いかもしれない。「超人スポーツ」とは、簡単にいえば、VRやAR、ロボットなど最新のテクノロジーを使って能力を拡張した人間が競い合うスポーツのこと。装着型ロボットをまとったり、アシストスーツを身につけたりした人間が、超人的な技を披露して戦い合う。
たとえば、「テクノスポーツで世界に夢と希望を与える」というビジョンを掲げる株式会社meleap(メリープ)は、HADO(ハドー)をはじめとするARスポーツ事業を展開している。
HADO(ハドー)ウェブサイト
HADOは、頭にヘッドマウントディスプレイ、腕にアームセンサーを装着して両手から「波動」を出し、目の前にある物体を破壊したり、相手を倒したりするスポーツだ。
通常の試合では3対3のチームに分かれ、手からエナジーボールを射出しながら対戦するが、その様子は迫力満点。まさに、マンガ『ドラゴンボール』に出てくる「かめはめ波」をモチーフにした対戦型シューティングゲームなのだ。
現在、日本では2020年の東京オリンピックに向けてスポーツへの関心が全体的に高まっている。そのなかでも、めざましく進化しているのが「スポーツ+テクノロジー」の動きだ。いま、スポーツにテクノロジーを導入するため、多くの企業が研究者とともに研究を進めている。
人間拡張工学が目指す「自在化」とは
こうした「超人スポーツ」のベースとなるものは、人間拡張工学だ。
人間拡張工学とは、本来、人間が持っている運動機能や感覚を、技術を使って拡張したり、増強したりすることを目的とした学術分野のこと。ロボット工学やVR、AIなどを用い、人と機械やコンピュータが「人機一体」となることで、人間の認識・行動能力を支援し、拡張することを目指している。
この人間拡張工学がめざしている概念は、「自在化」だ。
この「自在化」を語るためには、まず、20世紀型の産業モデルとして「自動化」について述べる必要がある。人間は18世紀半ばに始まった産業革命以後、さまざまな人工システムや機械システムを生み出してきた。
これにより、大きな力を要する仕事や精密さが求められる仕事など、人力では難しい仕事も次々と可能になり、世界には「自動化」の波が押しよせた。確かに「自動化」した社会ではめざましいスピードで文明が進化し、人々の生活は格段と便利になった。
だがその一方、機械が発達すればするほど、人間には使いこなすことが難しくなってきたのも事実である。言い換えれば、テクノロジーはそれを自由に使用できる人たちによって独占され、そうでない人との間に深い格差を生んだのだ。
こうした“20世紀型産業モデル”の不具合を解消する概念が、「自在化」だ。
つまり「自在化」とは、これまで使いこなすことが難しかったテクノロジーを、誰でも自在に使えるように改良することであり、たとえば、従来難解な操作が必要だった機械の操作も「ボタンひとつ押すだけ」「タッチパネルで直感的に操作するだけ」など、以前と比較にならないほどシンプルになり、誰もが高度な技術の恩恵にあずかれるようになった。
だがその一方、自在化にも問題点がある。なにからなにまで自動化してしまって、本当に人間は幸せなのか、という点だ。
現在、AIやIoTがめざましい進化を遂げており、日常生活にもロボットなど先端技術がどんどん入り込んでいる。
たとえば、掃除ロボットや自動運転などは確かに人間のストレスを減らし、負担を軽減しているが、その一方、人間の行動のすべてをロボットが代替するようになったら、人間は本当に幸せかというとそうではない。
運転が好きな人は、自動運転機能に任せるよりも自分で運転したいと思うだろうし、人間の代わりにロボットが美味しい食事を味わったり、スポーツを楽しんだりしても、当の本人は嬉しくない。
つまり、なんでも均一に自動化することはかえって人間の不幸を招くことになるのだ。そのため、危険な作業や面倒なことはどんどん「自動化」を進める一方で、人間が自分たちの体でやりたいことはいつでも自由にできるという「自在化」が必要であり、「自動化」と「自在化」の併用が今後、ますます求められていくのである。
この「自在化」をさらに徹底していくにあたり、まず「人間のできること」をどんどん拡張させていこう考えに基づいたのが「人間拡張工学」だ。
「人間拡張工学」は人間そのものを「超人化」して、望んだことを可能にしていくことを目指しているが、実は、人間拡張工学による人間の「超人化」は、世界的にみても、日本の得意分野であるといっていい。
なぜなら、先ほど紹介したHADOが、マンガ『ドラゴンボール』に出てくる「かめはめ波」をモチーフにしたように、日本人は元来、漫画的な想像力に優れている国民性だからだ。
振り返れば、「ドラえもん」や「Dr.スランプ」などのように、ロボットや人工人間を主人公にした漫画は日本で古くから人気を集めてきた。
まさに、ロボットアニメは日本のお家芸といってもよく、こうしたロボットアニメからインスピレーションを受ける「人間拡張工学」や「超人スポーツ」は、今後も日本からどんどん生まれてくることに違いない。
一体、人間はサイボーグになれるのか?
こうした人間拡張工学がますます進化している現在、必然的に生まれる疑問がある。それは、「人間はサイボーグになれるのか」ということだ。
これについて考える前に、まず前提として、「人間のサイボーグ化」には2種類あることを理解しなければならない。
ひとつは、病気の症状や身体的ハンデキャップを緩和させる目的で行われるサイボーグ化。もうひとつは、人間の能力や利便性を拡張することを目的としたサイボーグ化だ。これらのうち、前者タイプのサイボーグ化は倫理的に受け入れやすいだろう。多くが医療行為の一環として行われ、周囲の人の理解を得やすい。
だが後者タイプについてはどうだろうか。いわば、付加機能を求めて行われるサイボーグ化は賛否が分かれるところだろう。
たとえば視力を失った人が目に装着する「アイボーグ(視点をそのまま録画し、映像をスマホのスクリーンに映せる)」や、耳が聞こえない人が装着する「人工内耳(内耳の蝸牛に電極を接触させ、聴覚を補助する)」であれば、目の前にいる人がそれらの道具を身につけていたとしても、誰も「この人はサイボーグだ」と認識しないだろう。
しかし、脳や筋肉などに人工の装置をつなぎ、まるで自分の身体のように扱う人間が目の前にいたら、他人はそれを「人間」と見るだろうか。それとも、「サイボーグ」と見るだろうか。
機械を装着した人間に対して差別が発生する可能性も否定できず、そうなると、「サイボーグ」と「人間」の境界線をどこに敷くか、世界規模で法やシステムの整備が求められるのは間違いない。
技術的にいえば、人間が身体の大部分を機械に置き換え、人間を「サイボーグ」にすることは可能だろう。特に、主要先進国においては年々平均寿命が伸びている現代では、不死を求める声も多く、体を機械に置き換えてでも長生きしたいと望む人は今後ますます多くなってくるだろう。そのひとつが、2019年11月、イギリスで行われた手術だ。
筋萎縮性側索硬化症(ALS)という全身の筋肉が動かなくなる不治の病に冒されたロボット科学者、ピーター・スコット=モーガン博士は、自身の体を少しずつ機械に置き換え、世界初の完全サイボーグ化手術に成功している。
Dr Peter B Scott-Morgan Twitter より
博士の「私は死ぬのではない、変容するのだ」という言葉は、世界に大きな衝撃を与えた。
この場合は病気を克服するためのサイボーグ化であり、周囲の理解を得やすいかもしれないが、今後は「若返り」や「不老不死」を目的にしたサイボーグ化手術を行う人も登場するかもしれない。
彼らは人間離れした能力を備え、決して衰えない若さを身につけ、文字通り永遠に生を謳歌し続けるのかもしれない。
だが、みずからの意思でサイボーグになり、人知を超えた活躍をめざす人たちを、人々は「同じ人間」「仲間」として見ることができるだろうか。人間のサイボーグ化を心理的に許容する世界が到来するには、まだ時間がかかりそうだ。
文:鈴木博子