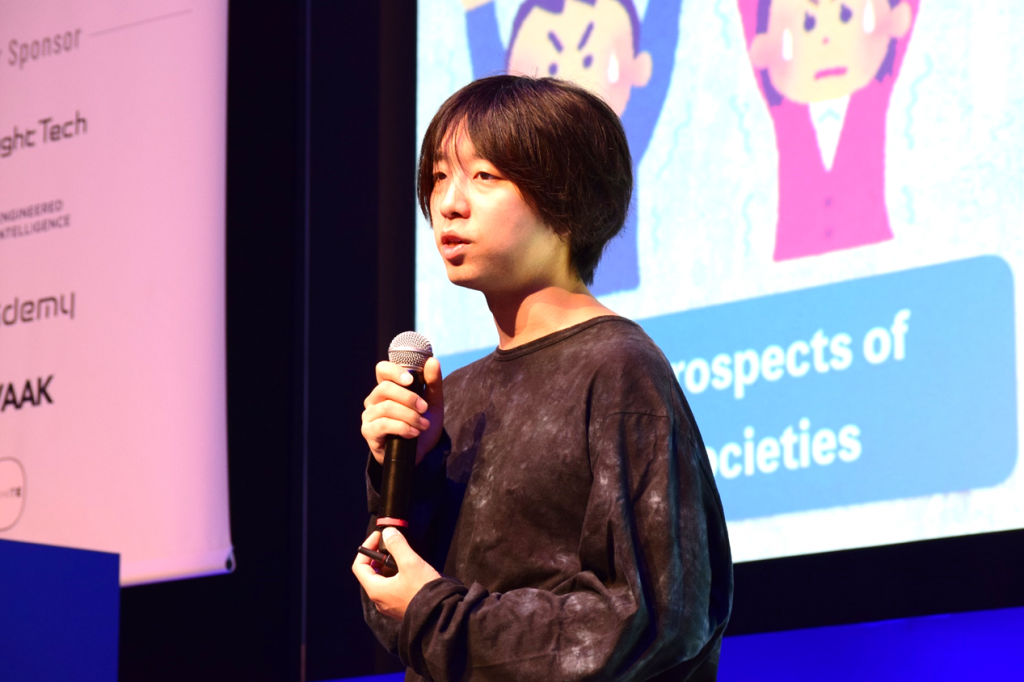2018年7月26日、Ledge.ai主催の大型AIカンファレンス「THE AI 2nd」が開催。筑波大学准教授/学長補佐・メディアアーティストの落合陽一氏が登壇し、これから日本が直面する「超AI時代」について語った。
高齢化社会を救うのはAIであるという認知が大切
落合陽一氏は「超AI時代」という言葉の火付け役だ。AIだけではマクロ問題に解決できない課題に直面した時、AI・ネットワーク・人をどう活用して解決すればいいのか。こうした課題に向き合うべき時代を「超AI時代」と呼んでいる。
日本はものづくり国家だが、高齢化・少子化が進む現在、撤退戦に陥りつつある。高齢になり身体的不自由を抱えた人を、どうサポートするか。生活タスクをこなす際の身体的・精神的・社会的ストレス軽減が課題だ。
これまでは社会問題を発見したら属人的能力に起因した<デザイナー>が新しい製品を設計・開発してマーケットに売り出し、問題解決していた。しかし、少子化が進めば<デザイナー>もたりなくなる。ユーザーが問題をみつけたあと、解決するのはAIになるだろう。労働力が低下する以上、高齢化した労働者や労働が行えなくなった高齢者を支えるためにはAIを導入し、人力に頼らず解決するアプローチをみつけなければならない。
AIが代替できるものづくりや生産活動はAIやAIに接続されたシステムに任せ、人間の、属人的な労働時間を削減するべきだ。
落合(以下、敬称略):「視聴覚や身体能力が衰えた時、快適な生活を維持するにはサポートが必要です。高齢者をサポートできる多様なAIを開発するために耳の聞こえない人や目の見えない人は『スマートフォンやスマートフォンを代替するようなシステムをどう操作すればいいか』といった研究をしています。
こうした研究は現在、一般認識アルゴリズムに分類されますが、データ収集を含めものすごく工数がかかるのが難点です。そういったことを元に社会実装を進めるにはAIの基盤だけでなく、コミュニティ開発もしなければならない。ただ、多様なAIの開発は、高齢化によって労働力が低下する社会において非常に重要なので、注力すべきでしょう」
限られた人的資源を有効活用するためにも、スケールメリットを考えて作業を効率化する必要がある。例えば聾学校の生徒の数は1万人程度と、市場としてみた場合にはそれほど大きくないものだ。しかし、今後高齢化が進むことで、残念ながら目や耳や身体が不自由になってしまう人は増加していくことだろう。その際に視聴覚や運動能力をサポートできるAIが存在していることは市場の拡大とともに、その重要性が増すことだろう。
落合:「視覚だけでなく身体も衰えていきますから、ご高齢の方が車椅子に乗って移動するシーンも増えます。自動運転や半自動運転の車椅子を開発していますが、こういったものを新規システムとして作り込むには一台当たり100~200万かかります。となると、コストを鑑みてすべてを機械化せず、横についてリモコン操作する人をつけ、その操作リスクを例えば物体認識アルゴリズムによって補助した方がコストを低く抑えられるわけです。
今まではハードとソフトの連携したプログラムが研究開発に求められましたが、これからはユーザーの身体能力や認知能力に基づいてスマートフォンやタブレットで直感的に操作できるようにするべきでしょう。無理にコンピュータビジョンで解決するコストを払うよりも対象にマーカーをつけ、それをタブレットで追従するロボティクスを開発するのも一つの手です。スマートフォンとロボットだけで解決できる問題が増えれば、高齢化社会に適応できる可能性が高まります」
機械で眼球や頭部をトラッキングする速度が速くなり、眼球と顔を認識しやすくなった。目線や頭の動きを追えば、個人が何に興味を持っているかが把握できる。この機能を搭載した1人乗りのコンパクトな移動支援機器「パーソナルモビリティ」であれば、周辺環境を認識しながら人間の移動を補助できるだろう。
落合:「耳が聞こえない人でも音を認識できる触覚プロジェクトもJST CRESTのチームで富士通の本多さんや大阪大学の菅野さんの協力のもとスタートしています。従来の触覚提示プロジェクトは恣意的なものが多いことが問題でした。例えば最寄り駅に着いたらあらかじめ決めた振動パターンが動作するといった一見するとユーザビリティが低いものが中心でした。
使い勝手を良くするにはユーザー自身がカスタマイズできるようプログラミングするしかなかったのですが、その開発環境まで提示することは今まで少なかった様に感じています。ここはIoTデバイスの製作コストは下がっているので改善の余地があります。もっとユーザビリティが高いデバイスとそれを包含するエコシステムを生み出せるはずです」
スマホを持った人類はイルカに似ている
AI技術は、学会で認められただけでは産業に直結しない。論文上で理論は完成するため8割程度仕上がってはいるものの、あとの2割は実装しなければわからない。しかし、現場に託しても、その実装コストは2割の側に8割乗ってくる。コスト面が難しく、だれも実装できずに終わってしまう可能性は高い。
落合:「科学を実用化し生活に役立てる技術・エンジニアリングの教育をすればうまくいく可能性は高くなりますが、エンジニアリングスキルを持った人材が産業分野でもスターになれるかは怪しいです。分野特有の課題ではありますが、AI技術を実装し、解決まで含めて議論できるコミュニティづくりをするしかありません」
AI技術を実装する際、落合氏が理想としてイメージするのがイルカだ。イルカの視認範囲は30メートル、触覚は100メートルあり、2.5キロ先の音が聞こえる。イルカは、新しいデバイスを身につけた人類=スマホ搭載型人類に近いと述べる。
落合:「イルカがこれだけ広い距離に反応できるように、音や光の境界は多様ですから、こういった人の五感への情報提示と自動認識タスクや空間認識タスクの融合領域はこれからAI分野の主軸になると思っています。どうやったらもっとデバイスをスマートに使い、安価に認識できるようになるか。それは電気的・コンピュータ科学的なシステムアプローチだけでなく、材料やプリンティング分野にもまたがる問題です。例えば、音を通すと、レンズみたいに音が集約するメタマテリアルも存在します」
世を捨てよ、クマを狩ろう。
現在企業に勤める個人に向けて、落合氏は「世を捨てよ、クマを狩ろう。」という言葉を提示した。
落合:「最近、堀江貴文さんの著書『多動力』など意識高い系の本が増えているのは、農耕民族として生きているものの、狩猟民族の血が抜けない人たちが多いからだと思います。歴史を振り返っても農耕と狩猟は対立構造ではありませんが、工業や農耕的アプローチによって先の利益や利潤のために定期的な監督や業務を繰り返すのみではなく、新たな目標を狩っていく精神は不可欠です。
それは大雑把にいえば、狩猟民族として、突発的なゴールや倒すべき目標に向かって繰り返し戦闘してきた歴史がDNAに刻まれているということなのかもしれません。しかし、今は毎日会社員として働いて安定した給与をもらい、住宅ローンを30年で完済する人生を送っている。こうした現状に本能的な疼きを感じるのではないでしょうか」
インターネットで特定の対象を非難する炎上騒ぎも、フラストレーションを発散するための行動だと述べる。スマートフォンを槍に見立てれば、インスタグラマーすらも狩猟民族だ。狩猟民族としての疼きを昇華したいなら、会社での業務とはまったく違う副業を行うのがおすすめだという。それは少数のコミュニティで狩を行い、それを農耕側の社会に還元する<マタギ的>アプローチに似ている。
落合:「副業できるからといってストレスフルな仕事をすると人格は壊れてしまいますが、まずはやってみて感触を確かめるといいでしょう。ここで重要なのがストレスマネジメント。本質的には何事もストレスを感じるものです。論文だって集中して書けるのはせいぜい4時間くらいで、ストレスマネジメントができなければ知的生産は叶いません」
ストレスマネジメントでもAIが活用できる。どのタスクをAIに任せれば身体的・精神的・社会的ストレスがかからないか。要はやりたいことに挑戦するためのツールとして、限界費用の少ないソフトウェアリソースとしてAIを捉えるのである。なにか物足りなさを感じているのであれば、副業でクマ狩りを始めるといい。
(取材・写真)木村和貴
(文)萩原かおり